 |
|
|
 |
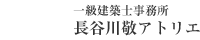 |
「木の家」って自然が好きな人なら誰でも一度は憧れますよね。夏は涼しく、冬は暖かい。さらに年間を通じて程よい湿度を保つことができる木は、まさに理想の建築資材と言えます。
そこで今回は東京都国分寺市にある「木の家作り」にこだわった一級建築士、長谷川敬さんにお話を伺い、自然と調和した木の家とその考え方についてお聞きしました。 |
|
|
|
|
|
 |
 |
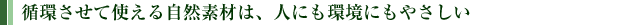 |
 |
 |
| ■ |
自然ねっと事務局(以下自然ねっと) |
| |
まず唐突かもしれませんが、自然の素材にこだわるのにはやっぱりそれなりの理由があるわけですよね? |
 |
 |
| ■ |
長谷川さん |
| |
 自然と人間は非常に長い間付き合ってきたわけですからやっぱりすむ所にも自然の素材を使うことが一番望ましいですよね。 自然と人間は非常に長い間付き合ってきたわけですからやっぱりすむ所にも自然の素材を使うことが一番望ましいですよね。
近年シックハウス症候群だとか化学物質過敏症とかに苦しむ人が少なくありませんが、それらの事例から分かることは、やっぱり化学物質の入った人工的なものほど人間の体には良くないということですよ。
有名な実験があって、ネズミを木の箱とコンクリートの箱と鉄の箱に入れて育てたところ、木の箱の中のネズミだけが生き残ってあとは三世代でみんな死んでしまったというものです。
それともうひとつ。“人の健康にいい”という点のほかにも“環境にいい”ということが挙げられますね。 |
 |
 |
| ■ |
自然ねっと |
| |
後の処理とかをふくめたことですか? |
 |
 |
| ■ |
長谷川さん |
| |
 そうですね。人工的な素材は生産過程でCO2を多く出します。また捨てた後に有害物質を出す恐れがあるだけでなく、“捨ててもなくならないゴミ”になってしまいます。そう考えると“有害でなくても害”になる。だから循環させて使うことのできる自然素材を使いたいですね。 そうですね。人工的な素材は生産過程でCO2を多く出します。また捨てた後に有害物質を出す恐れがあるだけでなく、“捨ててもなくならないゴミ”になってしまいます。そう考えると“有害でなくても害”になる。だから循環させて使うことのできる自然素材を使いたいですね。 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| ■ |
自然ねっと |
| |
完全にお金の面だけを考えたら、今はやっぱり木の家を建てる方がコスト的にはかかってしまうのでしょうか? |
 |
 |
| ■ |
長谷川さん |
| |
一概にそうとは言えないですね。どうしてかというとですね、木の家が高いのではなく、木の家は手間がかかるから高いのです。
現在は手間をかけずに儲ける家造りが主流なので、そういう工務店に"木の家造り"を頼めば確かに高くつきます。けれども、本当に"造る人"を主体にした小規模な大工・工務店や職人集団でつくれば、営業費や宣伝費などの経費もいらないので、手間を十分かけて、新建材の家と同じ位の金額でできます。また、社会的には化石資源を使った際の外部不経済というのを勘定に一切入れれば木の家は一番安いことになります。 |
 |
 |
| ■ |
自然ねっと |
| |
外部不経済? |
 |
 |
| ■ |
長谷川さん |
| |
さきほどいったゴミ処理が大変だとか生産する時も捨てる時も環境に負荷がかかるだとか・・・新建材のそういった面を考えたら必ずしも“木の家”の方が不経済とは言い難いですよね。そもそも国産の木が高いというのは全く嘘で、日本の木も外材と変わらない値段で流通しているんですよ。 |
 |
 |
| ■ |
自然ねっと |
| |
えっ!そうなんですか?日本の木の方が高そうな気がするのですが・・・・。 |
 |
 |
| ■ |
長谷川さん |
| |
 でも実際はそうではないんですよ。日本の木の値段を外材に合わせてしまっているんで。逆に“木の値段が安すぎる”だから日本の山が荒れ放題になってしまうわけです。 でも実際はそうではないんですよ。日本の木の値段を外材に合わせてしまっているんで。逆に“木の値段が安すぎる”だから日本の山が荒れ放題になってしまうわけです。 |
|
|
|
|
|
 |
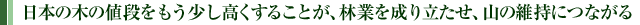 |
 |
 |
| ■ |
自然ねっと |
| |
長谷川 敬さんのホームページの中にはわざわざ遠くの木を使わずに近くの山の木を使いましょうと書かれていますよね。この辺りの理由というのも、輸入材と日本国内の木材を比較した際に値段がさほどかわらない、だったら近くの木の方がコストがかからないから使おうという流れになっているんですよね? |
 |
 |
| ■ |
長谷川さん |
| |
 確かに近くの木を使えば運賃も安くて済みますが、近くの森林こそ私たちが使う水を貯え、CO2を吸収し、水害を防止して直接私たちの環境を守っているのです。ですからただ安いからという理由だけではありません。むしろ僕は日本の木を高く買おうって言っているんですよ。日本の木をみんなでやりくりして、高く買おう!そして日本の山を元気にしよう!。そうすれば、世界の大事な森を破壊しなくて済みますからね。わざわざ遠くの木を使わなくても日本には成長しつつある人工林がたくさんあるんですよ。 確かに近くの木を使えば運賃も安くて済みますが、近くの森林こそ私たちが使う水を貯え、CO2を吸収し、水害を防止して直接私たちの環境を守っているのです。ですからただ安いからという理由だけではありません。むしろ僕は日本の木を高く買おうって言っているんですよ。日本の木をみんなでやりくりして、高く買おう!そして日本の山を元気にしよう!。そうすれば、世界の大事な森を破壊しなくて済みますからね。わざわざ遠くの木を使わなくても日本には成長しつつある人工林がたくさんあるんですよ。
そしてできればその木を林業が成り立つ値段で買うというシステムをつくる。そうすれば日本の山も助かるし、その山を源流とする水環境だとかその流域の生態系の維持にもつながるんですよ。山を維持するということは我々にたくさんの恩恵をもたらしてくれるのです。 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
| ■ |
自然ねっと |
| |
長谷川さんの建築事務所では必ず“近くの山の木”を材料としているそうですが、具体的にはどの辺りの木を使われているのですか? |
 |
 |
| ■ |
長谷川さん |
| |
ここでは東京の木をつかっています。 |
 |
 |
| ■ |
自然ねっと |
| |
奥多摩とかですか? |
 |
 |
| ■ |
長谷川さん |
| |
そうですね。あきる野市、桧原村、奥多摩町、日出町、八王子市、青梅市辺りの木を使っています。 |
 |
 |
| ■ |
自然ねっと |
| |
ちょっと意外でしたね。近くの木といっても日本国内の木を使用しているのかと思っていました。やっぱりそんなに近くの木を使っているのにも理由があるわけですよね。 |
 |
 |
| ■ |
長谷川さん |
| |
 そりゃあ、我々は多摩川の恩恵を受けている訳ですから。まずはその源流となっている山からスタートでしょ。やっぱり近くの山とその恩恵を受ける町の人とを結びつけるのが一番理解してもらうのにはてっとり早いですね。 そりゃあ、我々は多摩川の恩恵を受けている訳ですから。まずはその源流となっている山からスタートでしょ。やっぱり近くの山とその恩恵を受ける町の人とを結びつけるのが一番理解してもらうのにはてっとり早いですね。
そのために私たちは家を作りたいという人をよく山に連れて行くんですよ。そして山と親しくなってもらうんです。木の家を建てるというのには山にとってこんな意味があるんですよというのをまずは分かってもらいたいですね。もちろん押し付けはしませんよ。でも、共感してくれた方は家を建てた後も山を故郷のように大事に思ってくれて、よく「東京の木で家をつくる会」の植林イベントの時なんかには手伝いに来てくれますね。さらに、そういった所から自然と自分の家にも愛着が持てるようにもなりますよね。 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
編 集 後 記 |
|
 |
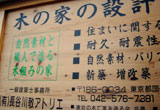 長谷川敬アトリエでは新築だけではなく少ない予算でも行なえるリフォームもやっているようです。自分の生活空間に少し自然を取り入れたいと考えている方には嬉しい話ですよね。床を板に張り替えたり・・・壁を漆喰にしたり・・・と、ちょっと手を加えるだけでも大分雰囲気を変える事ができるそうです。 長谷川敬アトリエでは新築だけではなく少ない予算でも行なえるリフォームもやっているようです。自分の生活空間に少し自然を取り入れたいと考えている方には嬉しい話ですよね。床を板に張り替えたり・・・壁を漆喰にしたり・・・と、ちょっと手を加えるだけでも大分雰囲気を変える事ができるそうです。
わざわざ田舎で暮らしたりしなくても、意外と自然を取り入れた生活というのは手軽にできるものなのかもしれません。要は自分自身がどういった生活を望むかということなんですよね。 |
 |
| ※一部写真は長谷川敬アトリエHPより転載させていただきました。 |
| 2003年取材 |
 |
 |
|