 |
 |
 |
 大山の山頂は秦野市、厚木市、伊勢原市の境にあり360°の大展望。新宿の高層ビル、伊豆の島々、富士山、箱根の山々などが眺められます。ピラミッド型の美しい姿が相模平野のどこからも見える大山は、昔から農民には農業の神、漁民には航行守護の神として崇められていました。山頂に本社、中腹に下社がある大山阿夫利神社はおよそ二千年前に創建されたと伝えられ、大山祇社、大雷神、高おかみの三神を祭神としています。 大山の山頂は秦野市、厚木市、伊勢原市の境にあり360°の大展望。新宿の高層ビル、伊豆の島々、富士山、箱根の山々などが眺められます。ピラミッド型の美しい姿が相模平野のどこからも見える大山は、昔から農民には農業の神、漁民には航行守護の神として崇められていました。山頂に本社、中腹に下社がある大山阿夫利神社はおよそ二千年前に創建されたと伝えられ、大山祇社、大雷神、高おかみの三神を祭神としています。 |
 |
登山道には、下社を1丁目、頂上を28丁目とする石柱が立っています。
幸い急な坂はありませんが、とにかく長い登りが続きます。大きな杉や展望のきくところもいくつかあり、5月頃にはトウゴクミツバツツジの花が見られます。
今回紹介するコースプランの他にもコースもあるので地図で調べてチャレンジするのもおすすめです。 |
 |
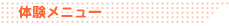 |
 |
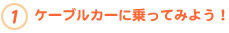 |
 |
小田急伊勢原駅前から出ているバスで終点の大山ケーブル駅で下車。近くには駐車場もあり、車で来ることもできます。土産物店や旅館、食堂が建ち並ぶ参道を登るとケーブルカーの追分駅に着きます。
追分駅から下社駅まではケーブルカーが便利。車中からは伊勢原方面の町並みがよく見えます。約6分で下社駅に到着。往復850円。 |
|
 |
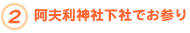 |
 |
下社駅の近くに食事のできる店があり、その横の石段を登ると境内が現れます。正面には立派な拝殿があるので、無事に山に登れるようにお参りをすることもできます。
中には大山名水が流れており、飲料水として汲んでいくのもいいかも知れません。 |
|
 |
 |
 |
境内の左手にある、何段あるのか数えてみたくなるような長く急な石段を登ります。この登山道は1丁目から始まり2丁目、3丁目と続く道で、8丁目の夫婦杉、10丁目の大杉、15丁目の天狗鼻突き岩などを横目に登山を続けます。
また、16丁目では裏参道と合流、石尊大権現の大きな石柱を見ることができます。25丁目でヤビツ峠から延びる道と合流するヤビツ峠分岐を越え、27丁目の銅製の鳥居をくぐると、ようやく28丁目で大山の山頂に到着します。 |
|
 |
 |
 |
下社から大山山頂までの行程は約1時間20分。
山頂には、阿夫利神社の本社である奥の院が祭られています。下社に比べると小さくて質素ですが、眺めは最高で山頂の周りをぐるっと回れば360°の大パノラマが待っています。山頂から眺める新宿の高層ビルや富士山、伊豆の島々は爽快です。 |
|
 |
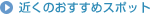 |
 |
 |
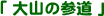 |
 |
 ケーブルカーの追分駅の下に大山の参道があり、石段の道の両側に土産物店や茶店、旅館などが賑やかに並んでいます。大山コマや猪鍋など、素通りするのには惜しいものがたくさんありますが、何と言っても名物は、大山名水で作った大山とうふ料理。これを食べれば登山の疲れなんてすぐに吹き飛んでしまうこと間違いなし。 ケーブルカーの追分駅の下に大山の参道があり、石段の道の両側に土産物店や茶店、旅館などが賑やかに並んでいます。大山コマや猪鍋など、素通りするのには惜しいものがたくさんありますが、何と言っても名物は、大山名水で作った大山とうふ料理。これを食べれば登山の疲れなんてすぐに吹き飛んでしまうこと間違いなし。 |
|
|
 |
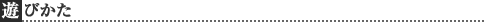 |
 |
 |
 |
 |
自然を満喫しながら野山を歩くことです。四季を通していろいろな表情を見せてくれる山は、何度訪れても飽きることがありません。道具さえ揃えてしまえばいつでも楽しめますが、けして無理をせずに自分の体力にあった場所を探しましょう。 |
|
 |
 |
 |
 |
| ■ |
準備は前日に済ませておきましょう。 |
| ■ |
自分のペースで歩きます。
歩幅は小さめにし、足はかかとから下ろさずに足裏全体に体重を移動させましょう。 |
| ■ |
水分はこまめに少しずつ取りましょう。がぶ飲みは疲労感が増す場合もあります。 |
| ■ |
登りが優先です。道幅が狭いところでは、登りの人に先に進んでもらいます。 |
|
|
 |
 |
 |
 |
| a) |
ザック・リュック |
 |
容量20〜30L程度 |
| b) |
靴 |
 |
スニーカーよりはトレッキング用のシューズが好ましい。 |
| c) |
レインパーカー |
 |
天候にかかわらず必ず持参した方がよい。防寒具にもなります。 |
| d) |
折りたたみ雨傘 |
 |
天候にかかわらず必ず持参した方がよい。 |
| e) |
水筒 |
 |
ジュースなどよりお茶がおすすめです。 |
| f) |
お弁当・非常食 |
 |
腐食しやすいものは避けましょう。 |
| g) |
タオル・ポケットティッシュ |
| h) |
救急薬品 |
 |
常備薬、ばんそうこう、消毒薬など |
| i) |
帽子 |
| ※ |
その他 |
 |
カメラ、ごみ袋、ヘッドランプ、地図など |
|
|
 |
 |
 |
 |
| ■ |
無理をしない(体力、天候など) |
 |
■ |
ゴミは必ず持ち帰る |
| ■ |
現地の草花を持ち帰らない |
 |
 |
 |
|
|
 |
| 2002年取材 |