| そばといえば長野県の「信州そば」が有名ですが、山梨県の「甲州そば」もまた捨てがたいうまさがあります。「甲州そば」は富士山麓の夏は涼しく、冬の寒さがきびしい気候や風土、そして水の良さが織りなすこしのあるそば。そこで今回は山梨県にある山中湖へそば打ち体験に出かけました。しかも山中湖は紅葉真っ盛り!富士山麓で紅葉に染まる山中湖と富士の湧き水を使った手打ちそば・・・目にも体にもいいこと間違いなしの体験となりそうです。 |
 |
| 山中湖は河口湖・西湖・精進湖・本栖湖とならんで富士五胡に数えられ、国内でも3番目の高所にある湖でもあり、湖面の標高は982メートル、湖面の面積も6.67平方キロメートルと五湖の中で最大の湖です。夏の平均気温は20度前後とすごしやすく、はやくから避暑地としてひらけた場所でもあります。夏から秋・初冬にかけてたくさんの観光客が訪れ、その数は年間400万人にもおよびます。 また、1956年に発見された天然記念物のフジマリモや白鳥の越冬最南端、そして最も標高の高い場所にある「白鳥の湖」として知られています。最近は「花の都公園」や「文学の森美術館」をはじめ「テディベアワールドミュージアム」や「サンタクロースミュージアム」など多くのギャラリー・美術館が立ち並び、訪れたことがある方も多いでしょう。 今回はそんな中で富士山が南西に真近に眺められる山中湖村の旭日丘・からまつの森路にある「体験工房アントヴ」へおじゃましてそば打ちを体験することにしました。 |
 |
| 出迎えてくれたのは「脱サラといえば聞こえはいいんですが・・・」とこの地で10年以上暮らす「アントヴ」の曽根さん。早速ログ風の建物の2階へ案内され、そば打ちを始めることに。まず最初に用意されていたのは大きな木鉢(こね鉢)と軽量カップに入った水、そして打ち粉。「座って土間で直に打っても良いのだけど、うちでは若い人でも気軽に体験できるようにテーブルを使っている」とのこと。水は裏の井戸から引いた地下水。当たり前といえば当たり前だが、カルキ臭はまったくなく、飲んでみると少し甘みまで感じられるまさにミネラルウォーター。「そば打ちは水回しやへそだしなどの、いろいろ作る過程で言葉は多いけど、それはうん蓄。知っていたほうが良いけど、要はこねて、切って、茹でて、おいしく食べればいいのだから」と説明してくれた。 挑戦するのは「二八蕎麦」。江戸時代、2×8=16文で一杯食べられた屋台の呼び文句からきたという説と小麦2と蕎麦8の成分の比率で打つからという説があり、今回は後者。小麦粉2にそば粉8の比率で作ることにしました。まず、少しずつ水を加えながらそば粉に均等に水が含まれるようにするのが「水回し」。さらさらだったそば粉が水を含んで段々大きな粒になり最後は固めて大きな球状に。それをさらにこねて面だし・へそだしをへてここから平たく伸ばしていくことに。最初は手の甲で均等に丸くなるように伸ばし(鏡だし)、それから打ち棒でそばが四角くなるように伸ばしていく。ちなみのここで使う打ち棒は一本。3本使うのは「江戸流」でほとんどの地方そば打ちは一本ですべての工程を行なう。あとはたたんで切って茹でる。途中で何度も打ち粉をしたが、打ち粉をするから「そば打ち」なのか打ち棒を使うからなのかその諸説は様々なのだそう。作ってみた感じでは両方に真実味がある。粉はまさしく打つように振り掛けるし、そばを棒に巻いて延ばす作業は「打つ」という言葉どおり。ぜひそば打ちに挑戦して「打つ」を実感してみてください。切り方はできるだけ細く均等に。 最後に味はというと、香り・歯ごたえ・こし、自分で作ったとは思えない上品なうまさ。これも富士の湧き水のおかげ。おいしくいただきました。今年の暮れはここで体験した「そば打ち」のウデで「年越しそば」にチャレンジ!皆さんも自家製の「手打ちそば」で今年を締めくくりませんか? |
 |
 |
 |
| 1.蕎麦打ち開始 |
2.この状態が蕎麦になる? |
3.こねてしっかり丸まった |
 |
 |
 |
 |
| 4.しっかりのばします |
5.細く切ってゆでましょう |
6.できあがり!いただきます |
|
 |
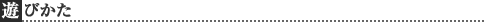 |
 |
 |
 |
 |
本格的に「そば打ち」をするなら実は用語だけでなく、かなり奥の深い世界。そばの実選びから石臼でそば粉を引くところからこだわるとさらに深くなります。そして道具選びも大変。家庭で気軽に行なうならこね鉢はステンレスのボウルで十分。打ち棒などもきちんとした檜などの棒でなくても大丈夫。大きなホームセンターなどに行くとそば打ちセットなどが手軽に入手できます。今回お邪魔した「アントヴ」のオーナーがいうように「こねて、切って、茹でて、おいしく食べれば」よいのです。多少見掛けが悪くても自分で一生懸命作った自家製そばの味は格別なはず。また、そば切り包丁も、たとえば会津地方に今も残る「裁ちそば」という手法では単なる菜切り包丁を使います。要はある道具をうまく利用してまずは作ってみることが肝心。徐々にそろえて最高の味を見つけていけばよいのです。そばを切るときに使う駒(小間)板もベニヤ板やまな板をうまく利用すれば形になるはず。まずは挑戦することです。 |
|
 |
 |
 |
 |
| ■ |
バスなどでお出かけの方は帰りの時刻を確かめましょう。 |
| ■ |
山中湖周辺のバスは本数が少なく、たまに来るバスも人影が見えないと素通りします。覚悟して山中湖散策も良いかもしれません。
今回は、「田舎だからいつ来るかわからないよ」と土産物屋のおばさんに笑われ、 2時間かけて紅葉散策を楽しみました。 |
|
|
 |
| 2004年取材 |