ハゼ科の魚は北海道から北九州まで汽水・淡水・海水に生息し、400近い種類があります。ハゼの種の特徴・見分け方・分布・名前の由来などだけで一冊の本があるほどです。
ハゼは種類によって、川や湖の他に、河口・干潟・内湾・磯・タイドプール・珊瑚礁など様々な場所に生息していますが、その中で今回狙うのはマハゼ。汽水域、内湾部の砂泥地に生息するハゼです。左右の胸びれが一緒になった吸盤状のヒレがあり、体長10cm〜20cm位が良く釣れる大きさです。東京では専門に狙う舟まであり季節の風物詩になっていて、釣りたてを船上で食べるのは格別の趣がありますが、陸釣りでも十分楽しむことができます。 |
 |
今回訪れたのは東京・江戸川区の新左近川親水公園。
「親水公園」は江戸川区が生みの親です。その中で新左近川親水公園は4番目の親水公園で、臨海町コミュニティ会館前に広がり、 区内にある幾つかの親水公園の中で唯一、ボートに乗ることができます。また公園内には芝生広場や遊具広場もあり、 ピクニック気分でバーベキューも味わえ、アイスキャンデー売りの鐘の音を聞きながら釣り以外でも一日過ごすことができます。
一見、普通の池のように見えますが、水門を通して荒川河口から海水が入り込み汽水域を作り出しています。 この水門からハゼの稚魚たちが5月ごろ入り込んでくるようです。ハゼ釣りのポイントはこの水門付近と、公園の真ん中にかかる中左近橋下、芝生広場前にいくつかある釣りデッキですが、 地元の人らしい完全装備の釣り師は移動しながらそこらじゅうで釣りまくっています。
投げ釣りは禁止となっていて、ときおり管理事務所からの放送が流れます。
水中を覗き込むとモエビやテナガエビ、カニの姿があり、割り箸にタコ糸をつけ、するめを餌に釣る家族連れも多く見受けられます。 |
 |
「針と糸があれば釣れる」といわれるハゼですが、本当にそのとおりで、目の前に投げてもすぐにあたりがあります。水深50センチ前後を狙ってウキ下とポイントをあわせるのが良いようです。外道(?)にスズキの若魚(フッコ)や幼魚(セイゴ)、ボラも釣れてきます。鯉やフナ、金魚も釣れることがあるそうです。餌はミミズでも十分ですが、近くで釣っていたお兄さんからもらったゴカイのほうが良く釣れました。
一本竿、一本針の浮き釣り仕掛けで釣りましたが、ハゼ用片天秤などで脈釣りも良いようです。
汽水域だけに潮の満ち干き気があり、昼間釣っていた岩場は夕方には完全に水の中へと消えていきました。 |
 |
| ※汽水域 河川などから流出する淡水と海洋の海水とが混じるところで、汽水(塩分濃度0.2%〜30%)が 恒常的にあるいは季節的に存在する河口域や内湾のこと。 |
 |
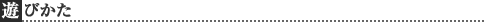 |
 |
 |
 |
 |
ハゼは最盛期には岸近くの浅場まで寄ってきます。場所にもよりますが、ほとんどの場合、川で使用するようなのべ竿で十分です。ハゼ釣りは手返しの早さで数をあげるのがコツなので、手持ちで疲れない軽い竿を使用するのがベストです。餌はミミズ・ゴカイ・青イソメなどです。日持ちが良いのはミミズで、冷蔵庫などで十分保管できます。他の餌は使い切る分量で持参しましょう。また、どの餌でも飲み込まれない限り一度付けたエサで何匹も釣ることができます。特に青イソメはオススメです。
ハゼは底にいます。ウキ釣りの場合はウキ下をそこすれすれに調整するのが数釣りのポイントです。脈釣りの場合は底を探りながら誘いつつ釣ります。仕掛けをゆっくり上下させ、これを繰り返します。あたりが遠のいたら、少しずつ移動しながら釣りましょう。時間を置いてから同じ場所で釣っても釣れ始めることがあります。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 【新左近川親水公園での注意事項】 |
| ■ |
予約や受付などは必要ありませんが、釣具などは持参しましょう。 |
| ■ |
ごみなどは捨てずに必ず持ち帰りましょう。 |
| ■ |
投げ釣り・ギャング針による釣りは禁止です。 |
| ■ |
柵などあり、救命浮き輪なども随所にありますが、小さいお子さんなどは目を離さないようにしましょう。 |
|
|
 |
| 2004年取材 |